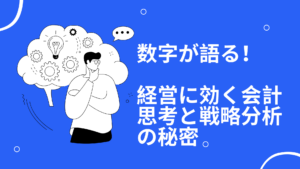副業の所得申告が必要なラインとは
副業収入20万円以下の場合のルール
「副業で売上が伸びたときにやるべき経理と税金の準備」を考える際、まず知っておきたいのが20万円以下の場合の申告ルールです。副業の所得が年間20万円以下であれば、確定申告は通常必要ありません。ただし、住民税の申告は必要となるため注意が必要です。住民税の計算は自治体ごとに行われ、未申告の場合には後で追徴課税が発生する可能性もあります。副業をはじめたいんですけど、税金ってどうしたらいいですか、と疑問に思う方は、まずこの基準を確認することが重要です。
副業所得20万円以上のケースで必要な手続き
副業所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。この場合、給与以外の所得として副業分を国税庁に申告します。申告時には、経費を差し引いた所得額を正確に記載する必要があり、経費を正しく記録し適切な勘定科目を用いた経理が重要です。また、必要書類として副業収入の明細や経費証明書類を準備する必要があります。例えば、「雑所得」や「事業所得」として分類されるかどうかで金額や税金計算が異なるため、国税庁のガイドラインを参考にしっかり確認しましょう。
住民税への影響と申告の必要性
副業収入の申告が住民税にも直接影響する点は見落としがちなポイントです。確定申告を行わなければ、自治体が副業収入を把握できず、誤った税金計算がされる可能性があります。たとえ所得が20万円以下で確定申告不要であっても、住民税の申告が求められる場面があるため注意が必要です。特に会社員の場合、副業収入を申告しないことで、本業の給与に対する住民税計算に影響を及ぼし、結果的にトラブルに発展することも考えられます。税金面でのリスクを避けるためにも適切な申告が不可欠です。
事業所得と雑所得の違いに注意
副業の所得申告を行う際、「事業所得」と「雑所得」の違いを明確に理解しておくことが重要です。「事業所得」は本格的な事業活動から得られる所得であり、節税効果のある青色申告が可能ですが、「雑所得」は本業以外の収入で、青色申告は利用できません。例えば、継続的に顧客や取引先を持つ営業活動で得た収入は事業所得と見なされる可能性がありますが、一時的な副収入は雑所得と分類されます。この判断によって税率や経費計上の範囲が異なるため、専門家の助けを借りて慎重に判断することが大切です。
会社員が確認すべき源泉徴収のポイント
会社員が副業を始める際には、源泉徴収に注意が必要です。多くの副業収入には源泉徴収が適用されておらず、本業の給与のように天引きで税金が処理されていないケースがほとんどです。そのため、副業で得た収入については自ら申告し、税金を納める必要があります。また、会社に副業が知られることを避けたい場合は、住民税の特別徴収を普通徴収に切り替える手続きも考慮すべきです。このように副業に伴う税務手続きに精通し、適切な管理を行うことが、会社員としての本業を守る上でも重要です。
副業の経費計上とは?理解して負担軽減を図る
副業を始めると、売上から必要経費を差し引いた金額が所得となり、その所得に対して税金が課されます。このため、副業で売上が伸びたときにやるべき経理と税金の準備として、経費の正確な計上が重要です。経費を適切に管理し申告することで、税負担を減らせる可能性が高まります。ここでは、経費計上について基本的なポイントを解説します。
経費に含まれる項目例と注意点
経費に含まれる具体的な項目としては、事業に直接関係する支出が挙げられます。例えば、仕事用のパソコンやスマートフォンの購入費、通信費、電気代などが該当します。また、書籍代や勉強会の参加費、交通費も経費として認められる場合があります。ただし、プライベートで使用する割合が高い場合は全額を経費にすることはできません。そのため、業務に紐づいた支出である証拠を領収書やレシートとしてしっかり保管しましょう。必要に応じて勘定科目を正しく仕訳することも大切です。
減価償却費を正しく把握する
減価償却費は、主に長期間使用する設備や資産を経費に計上する際に適用される仕組みです。例えば、取得価額が10万円以上、使用可能期間が1年以上のパソコンやオフィス家具などがこれに当たります。これらは購入した年度に全額を経費とするのではなく、数年にわたって分割して計上します。一方、取得価額30万円未満の少額資産に関しては、合計が300万円に達するまで全額をその年の経費にすることも認められています。このようなルールは国税庁で明確に定められているため、確認しておきましょう。
青色申告と白色申告の違いと節税効果
副業の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は、事前に申請を行い、帳簿をきちんと作成・保存している場合に使用できる方法で、最大65万円の控除が受けられるなどの節税効果が大きいのが特徴です。一方、白色申告は手続きが簡易な反面、控除の恩恵を受けにくいため、所得が高額になる副業の場合は青色申告を選択することで負担を軽減することができます。どの申告方法を選ぶかは、売上や経費の状況を踏まえて検討しましょう。
帳簿の作成・保存が重要な理由
副業で得た所得や経費を正確に記録するためには、帳簿の作成が欠かせません。これにより、必要な経費を漏れなく計上することが可能になり、結果として税負担の抑制につながります。また、国税庁が定めるルールに従い、帳簿や領収書を原則として7年間保存する必要があります。このような準備を怠ると、税務調査の際に不利益を被るリスクがあるため注意が必要です。
経費を最大限活用するためのヒント
経費を最大限活用するためには、日々の取引を明確に記録し、経費項目を漏らさず把握することが重要です。例えば、経費に該当するか微妙なケースでは、税理士に相談するのも一つの方法です。また、会計ソフトを活用することで、仕訳のミスを減らし効率的に経理を行うことが可能です。さらに、自分が使用している設備やサービスが業務と関連している場合は、事業用としての割合を明確にし、その部分を経費として計上することで余分な負担を減らすことができます。
副業で利益が増えた場合の選択肢
利益が高額になった場合の会社設立の検討
副業で売上が伸びた場合、個人事業主としての活動だけではなく、会社を設立する選択肢を検討することも重要です。特に、副業収入が増え、節税や信用力の向上が必要になったときには会社設立を考えるタイミングと言えるでしょう。会社設立により法人税が適用されるため、ある程度以上の利益が出ている場合には、個人の所得税よりも税負担を軽減できる可能性があります。
法人化のメリット・デメリット
法人化の主なメリットの一つは、所得の分散による節税効果です。役員報酬を設定することで個人と法人の税負担を調整し、全体の税額を抑えられる可能性があります。また、法人名義での契約が可能になることで、取引先からの信用力が向上する点も強みです。一方で、法人化にはデメリットもあります。設立手続きに要する費用や、経理業務の複雑化がその代表例です。経理の管理に不安がある場合は、会計ソフトの活用や専門家への依頼も視野に入れると良いでしょう。
個人事業主から法人へ移行する手順
個人事業主から法人へ移行する際、まずは会社の種類(株式会社、合同会社など)を選定し、定款を作成します。その後、公証役場で定款の認証を受け、法務局で登記手続きを行います。これにより法人としての地位が確立されます。また、次に重要なのが移行後の経理業務の整備です。法人化後は、雑収入や雑所得だけでなく、勘定科目を明確に分けて記帳する必要があります。国税庁が示す基準に基づき、正確な会計処理を行いましょう。
法人化が必要なタイミングを見極める
法人化を検討するタイミングとして、副業所得が継続的に増加し、本業以上の収入を得る状況や税負担が増えたと感じたときが挙げられます。また、経費や勘定科目の管理が複雑化し、自身での対応が難しくなった場合も一つの目安です。具体的には、年間売上が1,000万円を超え消費税の課税対象者になった場合や、所得税の税率が増加するラインを超えた場合に法人化の効果が見込めるでしょう。自身の状況によって最適なタイミングを見極めることが重要です。
副業の確定申告と便利なツールの活用法
確定申告に必要な書類と手続き
副業を行う場合、所得に応じて確定申告が必要となります。まず、必要な書類としては、源泉徴収票(本業での給与所得がある場合)、副業収入の明細書(例えば、振込明細や領収書など)、そして経費を証明するための領収書やレシートなどが挙げられます。
副業の所得が「雑所得」や「事業所得」に該当するかを判断し、それぞれに応じた計上方法を用いる必要があります。雑所得の場合、総収入額から必要経費を差し引いた金額が課税対象です。副業所得が20万円を超える場合、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行いましょう。ただし、副業が20万円以下でも住民税の申告が別途必要となります。
会計ソフトを使ったスムーズな申告方法
副業で売上が伸びた際に、経理や仕訳処理をスマートに進めるには会計ソフトの活用が有効です。クラウド型の会計ソフトを使えば、収入や経費の記録を簡素化でき、確定申告の際に必要なデータを自動でまとめてくれる便利な機能があります。例えば、主要な勘定科目の仕訳が自動的に提案されるため、初心者でも正確な記帳が可能です。
また、会計ソフトでは電子申告(e-Tax)にも対応しているため、わざわざ税務署に出向く必要がありません。「副業をはじめたいんですけど、税金ってどうしたらいいですか」という疑問を抱える方にとって、初期投資として会計ソフトを導入しておくことをお勧めします。
税理士への依頼が必要なケースとは
副業所得が高額になる、または経理が複雑な場合には、税理士への依頼を検討すると良いでしょう。例えば、複数の収入源がある場合や、減価償却費を計上しなければならないケースなどでは、自身で対応するのが難しいことがあります。
また、税務上のリスクを回避し、正確な申告を行うためにも、プロに任せたほうが安心です。税理士への依頼費用は規模によって異なりますが、小規模の副業の場合、確定申告手続きは5万円から10万円ほどが相場と言われています。初めて副業所得を申告する場合や、売上が大きくなった場合には税理士に相談してみるのも一つの選択肢です。
税務調査に備えておくべき対応方法
副業で一定の収入が発生している場合、思わぬタイミングで税務調査が入る可能性があります。税務調査に備えて適切な対応をするためには、日頃の帳簿作成・保存が欠かせません。「仕訳例」に従って正確な記録を残し、証憑(領収書や請求書など)も整理しておきましょう。
雑所得や事業所得の区分が曖昧だと税率が変わる可能性があるため、国税庁のガイドラインを参考にしておくことも重要です。また、何か疑問がある場合は、前もって税理士に相談することでリスクを軽減できるでしょう。
オンラインサービスを利用した申告の効率化
近年、確定申告に関連するオンラインサービスが増えています。これらのサービスは、収支データを簡単に入力できたり、節税対策をアドバイスしてくれたりするため、手続き全体を効率化できます。
例えば、取引データを自動でインポートして勘定科目に振り分けてくれるツールを使えば、経理の負担が大幅に軽減されます。また、国税庁が提供するe-Taxを利用すれば、電子申告での提出も可能です。「副業と税金に関する手続きが不安」という方でも、直感的な操作で進められるため、初心者でも安心して活用できます。
投稿者プロフィール

- 公認会計士協会準会員
freee認定アドバイザー
2017年に公認会計士試験に合格し、監査法人で複数年にわたって監査経験を積んできました。また公認会計士試験の合格前後に2社設立と3つの新規事業を行った経験があります。1社事業は売却、1社はクローズしました。
現在は独立し、会計士としての専門知識と自身の起業・事業経験を活かし、会計・財務支援をはじめ、起業・経営に関するアドバイスも行っております。
具体的には、資金調達・補助金申請サポート、財務分析、事業計画の作成支援、記帳代行など、実務的かつ実践的な支援が可能です。
最新の投稿
 会計等記事2025年5月1日初心者必見!スモールビジネスで利益を出すための成功ガイド
会計等記事2025年5月1日初心者必見!スモールビジネスで利益を出すための成功ガイド 会計等記事2025年5月1日資金ゼロから挑戦!成功するスモールビジネスアイデア5選
会計等記事2025年5月1日資金ゼロから挑戦!成功するスモールビジネスアイデア5選 会計等記事2025年4月30日副業から本格起業へ!スモールビジネスを目指すための成功ガイド
会計等記事2025年4月30日副業から本格起業へ!スモールビジネスを目指すための成功ガイド 会計等記事2025年4月29日2025年注目の低リスクスモールビジネス!成功を掴む事業アイデア10選
会計等記事2025年4月29日2025年注目の低リスクスモールビジネス!成功を掴む事業アイデア10選