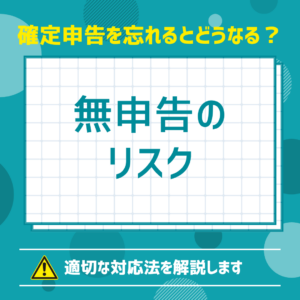電子帳簿保存法とは?概要と改正のポイント
電子帳簿保存法の歴史と目的
電子帳簿保存法は、1998年に施行された法律で、紙の帳簿や領収書を電子データとして保存することを認めるために作られました。この法律の目的は、帳簿や書類管理の効率化を図ると同時に、税務調査の透明性を高めることにあります。当初は紙媒体での管理が中心でしたが、デジタル化が進む中で、電子保存への対応が求められるようになりました。近年では、スキャナ保存や電子取引データの保存が現実的かつ実用的な選択肢となり、多くの企業が導入を進めています。
2022年改正と2024年義務化の背景
2022年1月1日の法改正では、電子帳簿保存法に大きな変更が加えられました。この改正の背景には、デジタル化の急速な進展と、働き方改革やペーパーレス化の推進があります。特に、電子取引データの保存義務化が導入され、これに関連する業務の正確さと効率性が求められるようになりました。ただし、事業者が対応準備を整えるための猶予期間が設けられ、2023年末までの間は完全な義務化が先送りされました。そして、2024年1月1日からは猶予期間が終了し、すべての対象事業者が法律に基づいた対応を求められることになります。
改正における主な変更点
今回の改正では、主に以下のポイントが変更されました。第一に、電子取引データの保存が完全に義務化されたことが挙げられます。これにより、PDFやメール添付で受け取る請求書や領収書なども適切に保存する必要があります。また、タイムスタンプの要件が緩和され、事業者にとって現実的かつ柔軟な対応が可能となりました。一方で、データ検索機能の整備などが引き続き求められ、保存方法についての遵守が徹底されることになりました。そのため、会計ソフトの導入や事務処理体制の構築が重要なポイントとなります。
電子取引データ保存の完全義務化とは?
2024年1月1日からは、電子取引で発生したデータを紙面に出力するのではなく、電子データのまま保存することが完全に義務化されます。この変更は、インターネットを通じて取引が一般化する中で、不正防止や税務調査の効率化を図るためのものです。例えば、メールで受け取る請求書や契約書のPDFデータ、電子請求書システムによる書類などがこれに該当します。この義務化により、適切な保存ソフトやシステムの導入が強く求められます。また、保存したデータの検索性や訂正・削除の履歴管理などが法律で定められた基準を満たす必要があります。電子帳簿保存法への対応が不十分な場合、法令違反となるリスクがあるため、早急な対応計画を立てることが鍵となります。
電子帳簿保存法対応の準備:必要な手続きとポイント
適用範囲と対象書類の把握
電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの保存が2024年1月から義務化されます。適用範囲には、税務に関連する帳簿や書類が含まれ、具体的には、請求書、領収書、契約書などの「帳簿」と「証憑」が該当します。また、PDFやメールで授受される電子データも対象となるため、これらの書類を適切に電子保存することが必要不可欠です。特に、中小企業や個人事業主の方は、日々の業務で使用される書類が対象となるか、事前にしっかり把握することが重要です。
対応を始めるための第一ステップ
電子帳簿保存法への対応を始めるには、まず自社で取り扱う対象書類をリストアップし、その保存方法や管理体制を見直すことが第一歩となります。次に、関連する会計ソフトウェアやスキャナを選定し、必要なシステムを導入していきます。また、改正法で求められるタイムスタンプやデータ検索機能を備えたシステムが必要となるため、適切なツールを選ぶことが重要です。2025年の完全義務化を見据え、早めに準備を進めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
事務処理規程の作成と管理体制の構築
電子帳簿保存法では、保存データの管理と税務調査時の対応が求められるため、事務処理規程の整備が不可欠です。この規程では、電子データの保存方法、タイムスタンプの付与手順、スキャナで読み取った文書の管理ルールなどを明文化します。また、これにより、社内フローの標準化を図ることができます。さらに、担当者の教育や責任区分を明確にし、適切な管理体制を構築することで、電子帳簿保存法の遵守を徹底できます。
電子帳簿保存ソフトの選定基準
電子帳簿保存法に対応するためには、自社のニーズに合った電子帳簿保存ソフトを選定することが重要です。その際に考慮すべき基準として、まず「法律に準拠した機能」が挙げられます。タイムスタンプの付与、データ検索機能、変更履歴の管理といった要件を満たすことが必須です。また、スモールビジネス向けの手軽さや導入コストも考慮すべきポイントです。近年では、スマホやスキャナで簡単に電子化を行えるソフトも増えているため、最新の製品を試したり、資料請求をして使用感を比較することをおすすめします。特に、2025年以降の税制改正にも柔軟に対応できるソフトの導入を目指しましょう。
導入時の注意点:トラブル事例と回避策
よくあるトラブル事例とその原因
電子帳簿保存法対応を進める中で、特に多く聞かれるトラブル事例として「対象書類の誤認識」「データ保存の不備」「タイムスタンプの付与漏れ」が挙げられます。例えば、対象外の書類を保存してしまったり、必要な電子データを紙媒体で保存したりするケースが発生しやすいです。これらの原因の多くは、電子帳簿保存法の要件を十分に理解していないことや、業務フローが明確に構築されていないことにあります。特に、2025年に向けて完全義務化が進む中、早急な対応が求められています。
税務調査での対応ポイント
電子帳簿保存法対応において、税務調査の際に重要なのは、保存したデータが即座に確認できる状態にあることです。具体的には、検索機能やタイムスタンプの証跡が整備されていることが求められます。税務調査では電子データの適切な運用状況を確認されるため、対応ソフトの導入に加えて、社内ルールの整備も欠かせません。また、税務調査時にトラブルを防ぐためには、日頃から保存データを定期的にチェックし、法令違反がないかの確認作業を行うことが効果的です。
過去データの扱い方と注意点
過去データの取り扱いは、電子帳簿保存法による義務化の中で特に注意が必要です。保存対象となる電子取引データが正確に保存されているか確認し、未対応分については早期に電子化を進めることが重要です。また、電子化する際には改ざん防止のためにタイムスタンプを適切に付与することが求められます。さらに、クラウドサービスや会計ソフトを活用する場合、過去の紙媒体データをスキャンして取り込むことで、電子帳簿保存法に対応しやすくなります。ただし、過去の紙文書を廃棄する前に電子化の完了とデータ検証を徹底的に行う必要があります。
クラウド保存とセキュリティリスク
電子帳簿保存法対応では、クラウドサービスを活用する企業が増えていますが、一方でセキュリティリスクに注意が必要です。クラウド保存の場合、データがインターネットを介して保存されるため、不正アクセスや情報漏洩といったサイバー攻撃のリスクがあります。このリスクを軽減するためには、二段階認証や暗号化技術を備えた安全性の高いクラウドサービスを選択することが重要です。また、利用するクラウドサービスが電子帳簿保存法の要件に準拠しているかを事前に確認し、導入前に十分な比較検討を行うことが求められます。
電子帳簿保存法を活用した業務効率化のヒント
会計業務のペーパーレス化の実現
電子帳簿保存法の義務化に伴い、会計業務のペーパーレス化が進んでいます。これにより、紙の書類を保管するスペースや検索作業の時間を削減でき、業務の効率化が図れます。たとえば、領収書や請求書をスキャニングして電子データ化し、そのデータを会計ソフトに直接保存・管理することで、経理業務の流れが簡素化されます。また、スキャナーやスマホを使えば書類のデジタル化も手軽に行えるため、紙媒体に依存しない運用が可能になります。
電子化推進によるコスト削減
紙の書類を電子データに置き換えることで、印刷費や紙代、郵送費といったコストの削減につながります。また、書類収納スペースを削減することもできるため、オフィスの運用コストも抑えられます。近年では、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトが多く登場しており、これらのツールを活用することで総合的なコスト削減が実現できます。特に、中小企業や個人事業主にとっては、電子化の導入がお金と時間の効率的な使い方に直結しています。
導入後の運用改善について
電子帳簿保存法に対応したシステムを導入した後も、運用体制の見直しや改善が必要です。対応ソフトのデータ検索機能やタイムスタンプ機能を有効に活用し、適切な管理を行うことが重要です。また、社員教育やマニュアル作成を通じて、システムの使い方の定着を図ることもポイントです。継続的な運用改善により、法律遵守はもちろん、業務プロセス全体の効率化とエラー削減が実現します。
対応が進む企業の成功事例
電子帳簿保存法対応を進めた企業では、業務効率化やコスト削減だけでなく、税務調査の際のスムーズな対応が可能となった事例が報告されています。たとえば、ある中小企業では、領収書や請求書などの書類の電子保存を徹底し、検索性とセキュリティ管理を強化しました。その結果、書類管理業務の省力化に成功しただけでなく、税務調査時の対応時間を大幅に短縮することができました。このような事例からも、電子帳簿保存法に対応する重要性と、それがもたらすメリットが明らかです。
投稿者プロフィール

- 公認会計士協会準会員
freee認定アドバイザー
2017年に公認会計士試験に合格し、監査法人で複数年にわたって監査経験を積んできました。また公認会計士試験の合格前後に2社設立と3つの新規事業を行った経験があります。1社事業は売却、1社はクローズしました。
現在は独立し、会計士としての専門知識と自身の起業・事業経験を活かし、会計・財務支援をはじめ、起業・経営に関するアドバイスも行っております。
具体的には、資金調達・補助金申請サポート、財務分析、事業計画の作成支援、記帳代行など、実務的かつ実践的な支援が可能です。
最新の投稿
 会計等記事2025年5月1日初心者必見!スモールビジネスで利益を出すための成功ガイド
会計等記事2025年5月1日初心者必見!スモールビジネスで利益を出すための成功ガイド 会計等記事2025年5月1日資金ゼロから挑戦!成功するスモールビジネスアイデア5選
会計等記事2025年5月1日資金ゼロから挑戦!成功するスモールビジネスアイデア5選 会計等記事2025年4月30日副業から本格起業へ!スモールビジネスを目指すための成功ガイド
会計等記事2025年4月30日副業から本格起業へ!スモールビジネスを目指すための成功ガイド 会計等記事2025年4月29日2025年注目の低リスクスモールビジネス!成功を掴む事業アイデア10選
会計等記事2025年4月29日2025年注目の低リスクスモールビジネス!成功を掴む事業アイデア10選