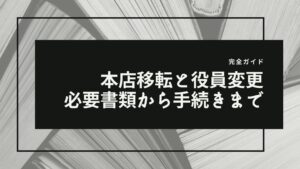事業目的を定める際の基本ルール
事業目的の適法性を確認する
事業目的を定める際には、まず適法性の確認が極めて重要です。定款の目的に違法性がある場合、定款の認証を受けることはできません。また、事業目的の適法性は許認可の取得にも直結します。例えば、特定の事業に必要な免許や許可が法律で求められるケースがありますが、その場合、事業目的にその業務内容が明確に示されていなければ、許認可を取得できない可能性があります。適法性を確保するために、設立前の段階で関係する法律や規制を十分に調査することが肝要です。
営利性を担保するための記載方法
会社設立における事業目的の記載には、「営利性」を担保することも欠かせません。営利性とは、会社が利益を上げる意図を持つことを意味します。営利性が不明瞭な記載は、会社設立登記が認められない場合があります。実際の記載例として、「○○商品の製造および販売」や「情報システムの開発および提供」など、具体的な収益活動が見えるような表現を心がけることがポイントです。また、営利性を意識することで、銀行融資や取引を行う際の信頼性も向上します。
明確性を持たせることの重要性
事業目的には明確性を持たせることが非常に重要です。明確性が欠けている場合、定款認証や登記がスムーズに進まないだけでなく、第三者から見て事業内容が伝わらず、取引や信用に影響を与える可能性があります。「〇〇業務の遂行」などの曖昧な表現は避け、具体的かつ簡潔な文言を使用してください。たとえば、「飲食店の経営」や「インターネットを活用した通信販売の運営」といった形で、事業内容が一目でわかる記載を心がけましょう。明確な目的の設定は、事業の計画性や実現性を対外的に示すうえでも役立ちます。
定款記載時に注意すべき用語の選択
定款に事業目的を記載する際の用語選択にも注意が必要です。不適切な用語や曖昧な表現は避け、法務局での審査がスムーズに進むよう、正確で一般的な表記を使用しましょう。たとえば、「IT技術の提供」といった漠然とした表現よりも、「クラウドシステムの構築および保守サービス」といった具体的な表現のほうが信頼性を高めます。また、将来的に多角化を予定している場合は、事業内容を幅広くカバーする表現も検討する必要があります。ただし、記載しすぎると信頼性が低下する可能性もあるため、バランスを考慮した用語選びが求められます。
業種別の具体的な事業目的の記載方法
事業目的を定款に記載する際には、業種ごとに特有の注意点があります。適切な記載は、会社設立時のスムーズな登記手続きの土台となるだけでなく、融資や許認可申請においても重要な役割を果たします。ここでは、製造業、IT業界、小売業・サービス業、そして複数業種を扱う場合の事業目的の記載方法について解説します。
製造業の事業目的記載例
製造業の事業目的を記載する際は、具体的にどのような製品を製造するのかを明示することが求められます。たとえば「金属部品の製造及び販売」「食品加工品の企画、製造および販売」といったように、製造品の種類と事業の範囲を明確に記載します。このように記載することで、商取引相手や金融機関からの信頼を得るだけでなく、適切な許認可手続きがスムーズに進むというメリットがあります。
IT業界での記載ルール
IT業界の事業目的には、大きく2つのポイントがあります。一つ目は、技術的専門性を分かりやすく示すことです。「ソフトウェアの開発および販売」「インターネットを利用した情報提供サービス」など、具体的な業務内容をきちんと明示します。二つ目は、将来的に展開可能な関連事業を広く視野に入れ、包括的に記載することです。たとえば、「クラウドサービスの運営」「AI技術を活用したコンサルティング業務」というように、最新技術や事業トレンドを捉えた目的が適しています。
小売業・サービス業の場合の注意点
小売業やサービス業の場合は、対象となる商品やサービス内容を具体的に記載することがポイントです。たとえば、「衣料品および日用品の販売」「飲食店の企画、運営および管理」といったように、販売品目や提供サービスの範囲を明確にすることで、第三者にとってより理解しやすくなります。また、サービス業については、提供エリアや対象顧客層を含めて記載すると、事業の透明性と信頼性が向上します。
複数業種を併記する際のポイント
複数の業種を併記する場合は、それぞれの業種ごとに事業目的を分けて記載する必要があります。たとえば「アパレル製品の企画、製造および販売」「ITシステムの開発およびシステムコンサルティング」のように、業種ごとに何を行うのかをしっかりと明示することが重要です。また、過度に広範囲な業種を含めると審査で指摘される可能性があるため、法務局での登記や実際の事業計画に役立つよう、現実的な範囲に収める必要があります。
事業目的を変更するケースと手続き
変更が必要となる主な理由
会社運営をしていく中で、事業目的を変更する必要が生じるケースは多くあります。主な理由として、事業の成長に伴う新規分野への進出、法令改正により許認可が必要となった場合、または会社の統廃合や業種の転換が挙げられます。たとえば、これまで製造業を主体としてきた会社が、IT分野にも進出したいと考えた場合、定款にこの新たな事業内容を記載する必要があります。また、目的外の事業を行うことで生じる法的トラブルを回避するためにも、目的の変更は慎重に行うことが求められます。
株主総会での承認プロセス
事業目的を変更する際には、株主総会の特別決議が必要です。特別決議は、通常の決議よりも厳しい要件を満たす必要があり、議決権の過半数を持つ株主が出席し、そのうち3分の2以上の賛成を得ることが条件となります。変更案を株主に理解してもらうため、事業目的の変更理由とその具体的な内容を明確に説明することが重要です。また、総会の議事録は変更登記の際に必要な書類となるため、記録を漏れなく正確に残しておくことも忘れないようにしましょう。
変更登記の具体的な手続き
定款の事業目的を変更した場合、法務局で変更登記を行う必要があります。具体的には、株主総会議事録、変更後の定款、登記申請書、印鑑証明書などを揃え、申請書を法務局に提出します。また、登記費用として登録免許税が約3万円かかります。手続き自体は複雑ではありませんが、書類の不備や記載ミスがあると受理されないこともあるため、必要書類を十分に確認することが大切です。業務の効率化を図りたい場合は、司法書士に依頼するか、オンラインサービスを活用することも選択肢の一つです。
変更をスムーズに進めるための注意点
事業目的の変更をスムーズに進めるためには、事前準備が非常に重要です。まず、現行の定款に定められた事業内容を見直し、新たに記載する目的が適法性や営利性を満たしているかを確認しましょう。また、法務局での審査を通過するためには、第三者にとって分かりやすく記載することも大事です。さらに、必要な書類の準備やスケジュールの確保を事前に行い、余裕を持って手続きを進めることを心がけましょう。会社設立時の目的記載と同様に、慎重かつ丁寧な対応が成功の鍵を握ります。
事業目的に関するよくある疑問と解決策
目的外の事業を行った場合のリスクとは
会社が定款に記載された事業目的外の業務を行った場合、思わぬ法律リスクが発生する可能性があります。具体的には、取引の相手方や第三者から事業の正当性を疑われ、契約が無効と見なされるリスクがあるのです。また、行政機関が関与する場合には、許認可が取り消される恐れもあります。特に会社設立時に許認可が必要な業種の場合、目的外の活動がトラブルの原因となるため、定款に記載された内容の範囲内で事業を行うことが求められます。さらに、金融機関から融資を受ける際にも事業目的の内容が重視されるため、適切に定款で目的を設定することが重要です。
事業目的を多く記載しすぎる問題点
将来性を見越して多くの事業目的を定款に盛り込むケースがありますが、これにはいくつかの注意点があります。一つは、事業目的が過剰に盛り込まれた結果、会社の方向性が不明確になり、取引先や投資家から信頼性を疑われる可能性があることです。また、目的が多すぎると法務局での審査が長期化する場合があります。法務局は事業目的が適法で明確であることを求めており、不適切な文言や重複があると申請が滞る原因となります。そのため、事業目的を記載する際は必要最低限に絞りつつ、会社としての将来性を十分に考慮した内容にすることが重要です。
既存の会社と似た内容がある場合の対策
事業目的の記載において既存の会社と類似の表現や内容がある場合、その適法性や独自性が問題視されることがあります。他社と区別をつけるためには、事業内容や提供するサービスを具体的に記載し、自社の強みをアピールすることが効果的です。また、競合会社との名称や目的が極端に似ている場合、場合によってはトラブルとなる可能性があります。法務局での審査をスムーズに進めるためにも、事業目的は独自性を持たせ、具体的かつ明確に記載することをおすすめします。また、競合他社の定款を参考にして、不自然な文言や法的な問題が潜在しないよう工夫するとよいでしょう。
法務局での審査をスムーズに通すコツ
法務局での審査をスムーズに通すためには、事業目的の内容を適法・明確・簡潔に記載することが重要です。まず第一に、目的の記載が現行の法律に適合しているか確認しましょう。次に、余計な表現を避け、行おうとしている事業を正確に記載することが大切です。また、用語の選択については、専門的なサービスに依頼したり、類似事例を確認することで合理性を担保できます。さらに、事業内容に許認可が必要な場合は、関連する制度や条件を事前に調査し、それを踏まえて定款を作成してください。これらの配慮が法務局でのスムーズな審査通過につながります。
投稿者プロフィール

- 公認会計士協会準会員
freee認定アドバイザー
2017年に公認会計士試験に合格し、監査法人で複数年にわたって監査経験を積んできました。また公認会計士試験の合格前後に2社設立と3つの新規事業を行った経験があります。1社事業は売却、1社はクローズしました。
現在は独立し、会計士としての専門知識と自身の起業・事業経験を活かし、会計・財務支援をはじめ、起業・経営に関するアドバイスも行っております。
具体的には、資金調達・補助金申請サポート、財務分析、事業計画の作成支援、記帳代行など、実務的かつ実践的な支援が可能です。
最新の投稿
 会計等記事2025年5月1日初心者必見!スモールビジネスで利益を出すための成功ガイド
会計等記事2025年5月1日初心者必見!スモールビジネスで利益を出すための成功ガイド 会計等記事2025年5月1日資金ゼロから挑戦!成功するスモールビジネスアイデア5選
会計等記事2025年5月1日資金ゼロから挑戦!成功するスモールビジネスアイデア5選 会計等記事2025年4月30日副業から本格起業へ!スモールビジネスを目指すための成功ガイド
会計等記事2025年4月30日副業から本格起業へ!スモールビジネスを目指すための成功ガイド 会計等記事2025年4月29日2025年注目の低リスクスモールビジネス!成功を掴む事業アイデア10選
会計等記事2025年4月29日2025年注目の低リスクスモールビジネス!成功を掴む事業アイデア10選